クリスマスが終わると、街は正月準備が始まり、しめ縄や門松、鏡餅を見かけるようになりますが、これらの正月飾りの由来や意味。
そして、いつから、いつまで飾るものなのか、どう処分したらよいかを解説します。
Contents
しめ縄・門松・鏡餅の由来と意味について

門松
古くから、お正月には「歳神様」(としがみさま)が、お越しになると言われ。
しめ縄・門松・鏡餅は、「歳神様」をお迎えするための準備だと言われています。
門松は、「歳神様」(としがみさま)をお迎えするための目印。
しめ縄は、神様が安心して頂ける「穢れ(けがれ)ない場所であることをお示し。
鏡餅は、前の年の米の収穫をお供えする者です。
メモ
正月に遣う祝箸は両方が欲しくなっていますが、それは神様と一緒にいただくと言う意味が込められています。
「歳神様」は、地域によって、歳徳神、とんどさん、恵方神、お正月様、など色々な名前で呼ばれています。その年の福徳(金運やしあわせ)を司る神様です。
メモ
恵方神は、恵方巻と同じ意味で、その年の神様のお越しになる方角を指します。
旧暦では、節分を境に新年としていたため恵方神と言われます。
しめ縄・門松・鏡餅は、いつから、いつまで飾るもの?

しめ飾り
しめ縄・門松・鏡餅は、松の内と呼ばれる期間内飾ると言われています。
松の内は、関東では12月13日~1月7日、関西では1月15日までとされています。
ですから、早いところでは12月13日に飾り付けされますが、今ではクリスマスが終わってから飾られる家が増えていますね。
ただし、飾り付けは12月29日と12月31日は良くないと言われています。
12月29日は、「二重苦」を連想させ、12月31日は「一夜飾り」と言い。
間に合わせで慌てて飾ったという意味合いで、失礼だとされています。
門松・しめ縄・鏡餅の処分

鏡餅
門松・しめ縄の処分は、小正月(1月15日)に行われる、「どんど焼き」で燃やすとのが良いと言われていますが、今では「どんど焼き」が行われるところも少なくなってきています。
そこで最近は燃えるゴミとして出すのが、一般的になっていますが、ゴミに出す前に、お塩で清めて手を合わせ、他の生活ごみとは別にして半紙などでくるんみ出すと縁起物として気も良く処分できます。
燃えるごみは、多くの場合、長さ50㎝未満に切り揃えないと、もっていってもらえないことが多いので、のこぎりで切って出します。
鏡餅は、鏡餅は、餅を神仏に供える正月飾りで、関東では「鏡開き」と言い、1月11日に餅を開いて食べます。
鏡餅は神様の霊が宿っているため、食べる時も包丁など刃物は使うと切腹を連想されるということで使いません。
また、木槌や手で割って食べますが、そのときも割るとは言わずに開くと言います。
まとめ
「歳神様」(としがみさま)を、お迎えして信念を幸多き歳となるよう、心を込めて飾り付けをおこない。
気持のよい新年をお迎えください。
良いお年を…。
関連記事


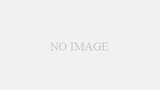



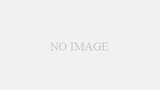


https://natsugg.com/kagami-biraki/


コメント